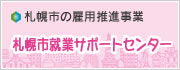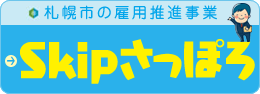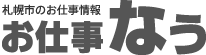ハラスメントとは
最近は「〇〇ハラスメント」という言葉を頻繁に耳にするようになりました。英語でharassmentは「悩ます(悩ませる)こと」という意味ですが、特に働く場面では「いじめや嫌がらせ」によって被害者の働く環境を悪化させる行為のことで使われることが多いようです。
職場におけるハラスメントによるトラブルは後を絶たず、都道府県労働局などに設置されている総合労働相談コーナーに寄せられる労働相談(民事上の個別労働関係紛争)の件数で12年連続最多となっているのが「いじめ・嫌がらせ」となっています。
今回は、職場におけるハラスメントについて正しく理解するため、「パワーハラスメント」、「セクシャルハラスメント」、「妊娠・出産・育児休業等ハラスメント」について見ていきましょう。
パワーハラスメント
職場におけるパワーハラスメントの定義は、厚生労働省のパワハラ防止指針(事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に以下のように定められています。
①優越的な関係を背景とした言動であって、
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
③労働者の就業環境が害されるものであり
①から③までの要素をすべて満たすもの
そして、パワーハラスメントは、以下ように代表的な6つの類型に分類されています。
- 身体的な攻撃(暴行・傷害)
殴打、足蹴りを行う - 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)
人格を否定するような言動をおこなう(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む) - 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりする - 過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)
長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずる - 過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)
- 個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)
労働者の性的指向。性的自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露する
これらの例は限定列挙ではなく、個別の事案の状況等によって判断されます。
また、労働施策総合推進法において、事業主は防止措置を講じることが義務付けられており、事業主に相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
セクシャルハラスメント
職場におけるセクシャルハラスメントの定義は、厚生労働省のセクハラ防止指針(事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に、「職場において行われる労働者の意に反する性的な言動により、労働者が労働条件について不利益を受けたり、就業環境が害されること」と定められています。
なお、「性的な言動」とは、性的な内容の発言及び性的な行動を指し、この「性的な内容の発言」には、性的な事実関係を尋ねること、性的な内容の情報を意図的に流布すること等が、「性的な行動」には、性的な関係を強要すること、必要なく身体に触ること、わいせつな図画を配布すること等が含まれています。
また、男女雇用機会均等法において、事業主は防止措置を講じることが義務付けられており、相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
妊娠・出産・育児休業等ハラスメント
職場における妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの定義は、厚生労働省のマタハラ等防止指針(事業主が職場における妊娠、出産等に関する言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針)に以下のように定められています。
- 「制度等の利用への嫌がらせ型」
雇用する女性労働者の労働基準法の規定による休業その他の妊娠又は出産に関する制度又は措置の利用に関する言動により就業環境が害されるもの - 「状態への嫌がらせ型」
その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したことその他の妊娠又は出産に関する言動により就業環境が害されるもの
また、男女雇用機会均等法において、事業主は防止措置を講じることが義務付けられており、相談したこと等を理由とする不利益取扱いも禁止されています。
正しい知識がなければ、無自覚にハラスメントをしてしまう・・・なんてこともあるかもしれません。事業主、労働者ともに「職場におけるハラスメント」について理解を深め、働きやすい職場づくりをしていきましょう!

- 私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!