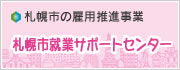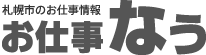労働時間と休憩時間について
今回は、過去に窓口で実際に相談があった「労働時間中の『休憩時間』の取扱い」について、「対象事例1」と「対象事例2」を基に見ていきたいと思います。
対象事例1
コールセンター業務の業務終了間近に込み入った案件が入り、所定の勤務時間8時~14時(6時間)を超え、45分の残業となってしまった。業務を終えそのまま帰宅しようとしたら、会社から「帰宅する前に1時間の休憩を取ってから帰宅するよう」指示があった。
対象事例2
コールセンター業務の業務終了間近に込み入った案件が入り、所定の勤務時間8時~14時(6時間)を超え、45分の残業となってしまった。業務を終えそのまま帰宅しようとしたら、会社から「帰宅する前に1時間の休憩を取ってから帰宅するよう」指示があった。
解説
まずは、休憩時間の取扱いについて、労働基準法を見ていきましょう。
労働基準法第34条1項
使用者は、労働時間が六時間を超える場合においては少なくとも四十五分、八時間を超える場合においては少なくとも一時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。
厚生労働省労働基準法に関するQ&Aに、以下のとおり記載があります。
休憩時間は労働者が権利として労働から離れることが保障されていなければなりません。従って、待機時間等のいわゆる手待時間は休憩に含まれません。
労働基準法第34条第2項
休憩時間は、一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定があるときは、この限りでない。
労働基準法第34条第3項
使用者は、第1項の休憩時間を自由に利用させなければならない。
労働基準法第34条より
対象事例1は、
休憩時間中の顧客対応は、上述の「手待ち時間」にあたります。休憩時間は、労働者の権利として労働から離れることが保証される時間となり、作業を行う場合は労働時間にあたります。すなわち、規定された休憩時間中の顧客対応は手待ち時間の対応と見なされ休憩をとっている時間とは判断されません。現状の休憩時間の取り方を企業主導で改善する必要があります。
対象事例2は、
労働基準法第34条第1項に、労働時間の途中に休憩時間を与えなければならない、とされているため、業務終了後は休憩時間には該当しません。
労働時間終了後の引継体制を含め、休憩時間とその取得方法の検討が必要となります。
休憩の重要性について
休憩する目的とは、継続した労働による肉体的・精神的疲労を労働の中断によって回復させることです。休憩をはさむことで、作業能率の向上と、労働者の健康な生活の確保を目指しています。
継続した労働は、労働者の健康を損なう恐れも高いと言われています。
また、肉体的・精神的に疲労が蓄積された状態は、作業能率の低下や労働災害の発生を招く危険もあります。
同時に休憩には、「労働者にとって生活の場でもある職場において、社会的・文化的な生活を保障する」といった意味があるようです。
休憩時間は一定の条件を満たした正社員、契約社員、派遣社員、アルバイト、パート、すべての労働者に平等に与えられます。就業されているすべての皆様が、平等に与えられた権利として「休憩」について、あらためて振り返ってみることが必要と思われます。

- 私は世の中にどのようなお仕事があるか研究している、なぅ先生です。
これから、お仕事について一緒に勉強していきましょう!!